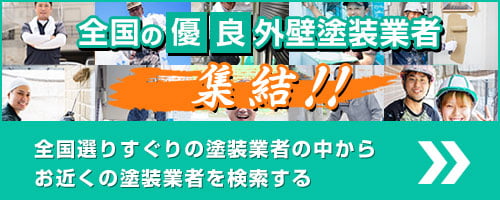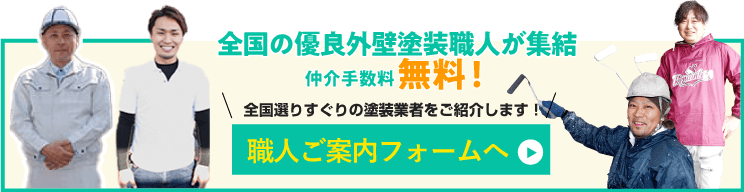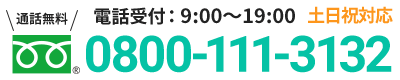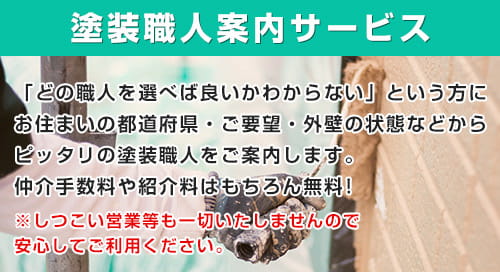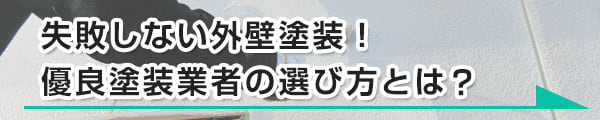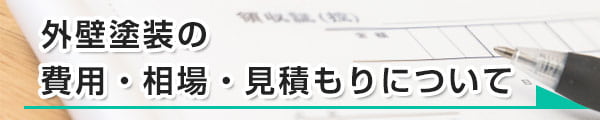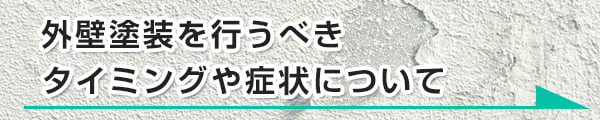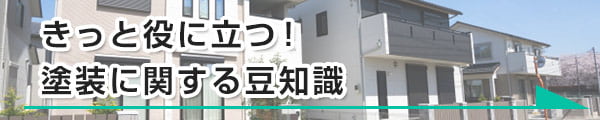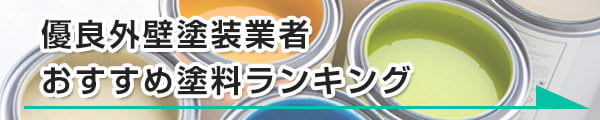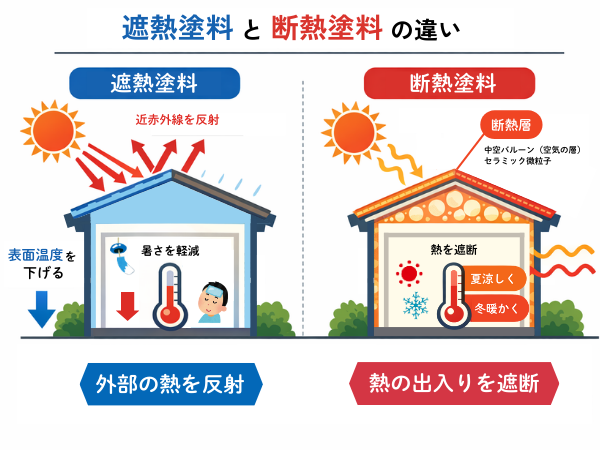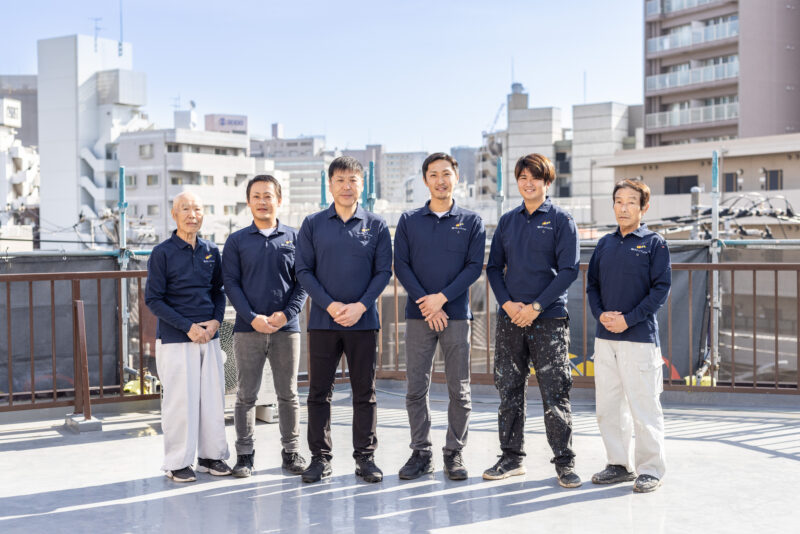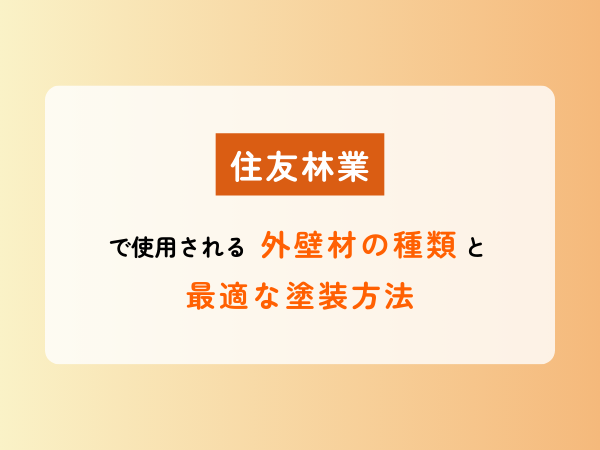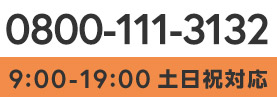目次
古民家塗装の特徴
古民家の塗装は、いわゆる現代的な住宅の塗装とは大きく異なる点がいくつもあります。ただ美しく塗ればよいというものではなく、「素材の特性」「伝統建築としての価値」「地域の景観」「経年変化を活かした風合い」など、複数の要素を同時に考慮しながら施工しなければなりません。ここでは、古民家ならではの塗装の特徴を3つの観点から詳しく見ていきましょう。
木材の多用と自然素材

古民家は、柱・梁・建具・軒天・外壁まで、たっぷりと無垢材や自然素材が使われているのが特徴です。特に日本の風土に合ったヒノキやスギ、ケヤキなどの木材が多く見られます。これらの木材は時間とともに味わいが深まり、独特の風合いを生み出していきます。
ただ、木材は美しい反面、紫外線や雨、湿気などの影響で劣化しやすい面も持ち合わせています。手入れをせずに放っておくと、表面にヒビが入ったり、ささくれができたり、最悪の場合は腐ったり虫に食われたりするリスクもあります。そのため、定期的な塗装でしっかり保護することが大切なのです。
ここで大事なポイントは「木が呼吸できる塗装」を選ぶこと。古民家の木材は現代の住宅でよく使われる集成材や合板ではなく、湿度を調整する力を持った無垢材が中心です。通気性のない塗料を使うと、中に湿気がこもってしまい、かえって木を傷める原因になることがあります。
ですから、自然由来の浸透型オイル系塗料や、湿気を通す性質に優れた塗料を選ぶことをお勧めします。また、塗りすぎて厚い膜を作らず、木本来の風合いを活かせる塗装技術を持った職人に依頼することも大切です。
漆喰や土壁などの伝統素材

古民家の外壁や内壁には、最近の住宅で見かけるサイディングやモルタルではなく、漆喰、土壁、砂壁、木摺り下地といった伝統的な素材が使われていることが多いのです。
これらの素材は見た目の美しさだけでなく、湿度を調整する力や断熱効果、火に強いといった実用面でも優れた特徴を持っています。ただ、塗装する際には少し難しい下地だということを覚えておきましょう。
なぜかというと、漆喰や土壁は表面がとてもデリケートで、ホームセンターで買えるような一般的な塗料だと上手く付かなかったり、後から剥がれてきたりすることがあるからです。また、湿気の多い場所では塗った面が膨らんだり、ひび割れたりすることも考えられます。
このため、下地の状態をしっかり確認して、専用の下塗り材を使ったり、湿気を通す天然素材の塗料を選ぶことが大切です。仕上がりの良し悪しは職人の知識と経験に大きく左右されますので、古民家の伝統素材をよく知っている専門業者に依頼することが非常に重要です。
文化財や景観条例への配慮
さらに、古民家塗装では見落とされがちですが、地域の文化財・景観保護条例との関係も非常に重要な要素です。
特に、京都市や金沢市など歴史的街並みが残る地域や、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に指定されているエリアでは、建物の外観を変更する際に市町村の許可が必要となる場合があります。
たとえば、
「外壁の色は周囲の景観に配慮して淡色系のみ」
「光沢のある塗料は使用不可」
「伝統的な素材や意匠を損なわないこと」
といった具体的な制限が設けられていることも。これらに違反してしまうと、行政からの是正指導や補助金の打ち切りといったリスクが発生します。
そのため、塗装前には必ず建築指導課や景観担当課に相談し、事前に申請・承認を得る必要があることを認識しておくべきです。対応経験のある業者であれば、こうした手続きをサポートしてくれる場合もあるため、施工前に確認しておきましょう。
古民家塗装で使用される塗料の種類と選び方

古民家は現代住宅と比べて使用されている素材や構造が大きく異なるため、塗料の選定には特別な配慮が求められます。風合いや歴史を残しつつ、耐久性・安全性を高めるには、目的に応じた適切な塗料を選ぶことが不可欠です。ここでは、古民家塗装でよく使用される3種類の塗料とその選び方のポイントを詳しく解説します。
浸透型塗料(オイルステイン・木材保護塗料)
浸透型塗料は、木材の内部に染み込んで着色・保護を行うタイプの塗料です。代表的なものとしてオイルステインや木材保護塗料(キシラデコール、ノンロット等)があり、木の呼吸を妨げず、木目の美しさをそのまま活かすことができます。
■ 特徴とメリット
- 木の質感・経年の風合いを残したまま防腐・防虫効果を付与
- 塗膜を形成しないため、塗り直しがしやすい
- 表面が剥がれにくく、メンテナンス性が高い
- 屋外の柱・梁・ウッドデッキなどに適している
■ 注意点
- 紫外線や雨による色褪せが起こりやすく、定期的な塗り直し(3〜5年ごと)が必要
- 着色性がやや弱いため、木の色ムラが残る場合がある
浸透型塗料は、「古民家の雰囲気を損ねたくない」「自然な質感を大切にしたい」という方に最適な選択肢です。
造膜型塗料(ウレタン・シリコンなど)
造膜型塗料は、木材や壁面の表面に塗膜を形成して保護するタイプの塗料です。現代の戸建住宅で主流となっている塗料の多くはこのタイプに分類され、ウレタン・シリコン・フッ素塗料などが代表格です。
■ 特徴とメリット
- 表面にしっかりとした膜をつくり、高い耐久性と防水性を実現
- 紫外線・雨風に強く、塗り替え周期が長め(7〜15年)
- カラーバリエーションが豊富
■ 注意点
- ツヤ感が出やすく、古民家の自然な風合いとミスマッチになることがある
- 呼吸性がないため、木部内部に湿気がたまりやすく、長期的にみると木の劣化を促進する可能性も
外壁の漆喰やモルタルの部分、屋根のトタン部など、木部以外の塗装や機能性重視の場面で使用されることが多く、職人の調整力が問われる塗料でもあります。
自然塗料(柿渋・亜麻仁油・蜜蝋など)
自然塗料は、天然素材のみを原料にした環境・健康に優しい塗料です。化学成分を含まないため、化学臭がなく、アレルギー対策としても注目されています。古民家再生の流れとともに、近年その需要が高まりつつあります。
■ 特徴とメリット
- 化学物質を含まないため、小さなお子様やペットがいる家庭でも安心
- 木材の呼吸を妨げず、柔らかな仕上がりになる
- 時間とともに深い色味に変化し、古民家の趣をより引き立てる
- 伝統建築との相性が良く、文化財指定建物でも使用されることがある
■ 注意点
- 防水性・耐久性はやや劣るため、屋外使用には定期的な再塗装が必要
- 色調の調整が難しく、仕上がりのバラつきが出る場合がある
- 材料費がやや高めになる傾向がある
「古民家に住むことそのものをライフスタイルとしたい」「自然素材の美しさを最大限活かしたい」という価値観を持つ人に好まれます。
選び方のポイント
古民家塗装において塗料選びは、単なる機能性だけではなく、建物の「歴史」と「個性」を活かす視点が重要です。以下の観点を参考に、現地調査や業者のアドバイスをもとに慎重に判断しましょう。
- 塗装する部位(木部/土壁/漆喰/トタンなど)
- 建物の使用目的(住居/店舗/文化財など)
- 保護の必要性(風雨・紫外線・虫害など)
- メンテナンスのしやすさ(DIY可能か、頻度は?)
- 景観や条例の制約(色や光沢の制限がある地域も)
【補足】柿渋塗料がなぜ古民家に選ばれるのか?
古来から防腐・防虫・防水の効果があるとされ、特に西日本を中心に古民家で重宝されてきた「柿渋塗料」。自然な茶褐色の仕上がりは、経年変化によりさらに味わいを増し、古民家ならではの時を重ねた美しさを表現するのにぴったりです。
柿渋は木部だけでなく、和紙・布・土壁にも使われることがあり、「伝統を受け継ぐ塗料」として再評価されています。
DIYと業者依頼の違い|古民家塗装はどこまで自分でできる?
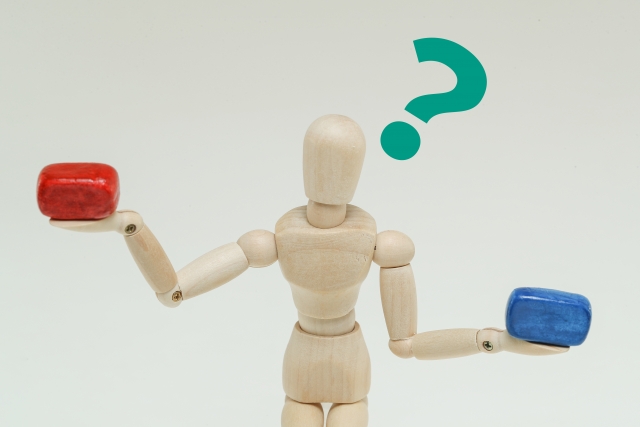
近年、古民家ブームやDIY人気の高まりを背景に、自宅の外壁や木部を自ら塗装しようと考える方も増えてきました。特に、古民家の持つ味わいや風合いを「自分の手で再生したい」という思いから、塗装にチャレンジする方も少なくありません。
しかし、古民家の塗装には、一般的な住宅とは異なる「素材の脆さ」や「構造的な難しさ」が存在します。安易なDIYはかえって住まいを傷めてしまうリスクもあるため、「どこまでがDIYで可能で、どこからが業者の仕事なのか」を知っておくことがとても重要です。
DIYでできるのは“ごく一部”に限られる
古民家塗装において、DIYで対応できる範囲は以下のように限定的です。
- 手の届く高さの木製フェンスやウッドデッキ
- 軒天や柱などの塗膜が剥がれた箇所の再塗装
- 内部の柱や梁の簡易な柿渋塗装 など
これらは比較的扱いやすく、専門的な足場や工具も不要なため、適切な塗料と手順を守ればDIYでも仕上げられる可能性があります。
ただし、次のような箇所はDIYでは難易度が非常に高く、専門業者への依頼が推奨されます。
- 漆喰壁の補修や塗装
- 高所の外壁や屋根まわりの木部
- 外部に露出している構造材(柱・梁など)
- 下地にカビや腐食、シロアリ被害が見られる箇所
特に漆喰は、「塗る」だけでなく「下地づくり」「乾燥時間」「重ね塗り」など複数工程を丁寧にこなす必要があり、素人が手を出すと剥がれや膨れの原因になってしまいます。
DIYのリスクは想像以上に大きい
「少し塗るだけなら大丈夫」と考える方も多いですが、古民家塗装には以下のようなDIYリスクが潜んでいます。
1. 不適切な塗料選びで素材を傷める
古民家の柱や梁、外壁には、無垢材や漆喰など呼吸する自然素材が多く使用されています。そこに造膜性の強すぎる塗料(ウレタンやアクリルなど)を塗ると、内部に湿気がこもり木が腐る原因に。見た目がきれいになっても、内部で傷みが進行してしまうのです。
2. 塗りムラやはがれで仕上がりが悪化
塗料の希釈率や塗布量、乾燥時間の見極めなど、プロが無意識にこなす作業にも精密な知識と経験が必要です。DIYではムラや刷毛跡が残ったり、1年程度で塗膜が剥がれてしまうケースも多く見られます。
3. 高所作業・足場の安全リスク
古民家は天井高があり、軒先も高いため脚立だけでは届かない場所が多数。無理な体勢で作業をすると、転落や道具の落下事故にもつながりかねません。安全に塗装するには、しっかりした足場と養生が不可欠です。
4. 構造材の劣化を見落とす
築年数の長い古民家では、目に見えない部分で劣化が進行していることもあります。例えば、外観だけ塗装しても内部の木材が腐っていたら数年で再工事が必要になります。プロは塗装前にこうした“構造の健全性”まで含めて診断するため、長持ちさせるには専門業者の目が欠かせません。
古民家塗装は「一部DIY」+「基本はプロ任せ」が最適解
塗装は一見シンプルに思えても、下地処理や素材の知識、気候への配慮、安全管理など、数多くの判断が必要な作業です。
古民家という繊細で価値ある住まいに手を入れるなら、「自分で楽しめる部分はDIYし、全体の耐久性と美観を保つ部分はプロに任せる」というバランスがもっとも現実的で安心といえます。
古民家塗装を依頼する業者の種類と特徴

古民家塗装を成功させる鍵は、業者選びにあります。
一口に塗装業者といっても、それぞれ得意分野や施工スタンスが異なります。特に古民家の場合、建材の知識だけでなく、文化的価値への理解、伝統的工法への対応力も問われるため、慎重な見極めが必要です。
以下に、古民家塗装を依頼できる主な業者の種類と、それぞれの特徴・注意点を整理して解説します。
1. 一般的な塗装業者
特徴
- モルタル・サイディング・ALCなど、現代的な外壁塗装の施工経験が豊富
- 高圧洗浄・下塗り・中塗り・上塗りなどの一般的な施工工程に対応
- ウレタンやシリコンなどの造膜系塗料の使用が主流
注意点
古民家のように「呼吸する素材(木材・漆喰・土壁)」を扱うには、現代建築の塗装とは異なる知識と技術が必要です。
- 通気性のある塗料を使わず、素材を傷めてしまう
- 漆喰や木部を一律のローラー塗りで施工し、美観を損なう
- 木の収縮・膨張による割れへの配慮がない
など、塗装後のトラブルが起きやすくなります。安さに惹かれて依頼したものの、「5年以内に再塗装が必要になった」という失敗談も少なくありません。
2. 古民家再生・リノベ専門業者
特徴
- 古民家の構造、使用素材、地域の気候などに精通
- 自然素材(柿渋、亜麻仁油、天然オイル)や、伝統工法(漆喰仕上げ、焼杉加工など)に対応
- 塗装だけでなく、「文化財としての価値」や「日本建築の美意識」も尊重した施工
メリット
- 塗るだけでなく“守る・活かす”視点で提案してくれる
- 素材の個性を活かした仕上がり(木目を残す、艶を抑える、など)
- 築年数に応じた劣化対策や補強の提案が受けられる
職人の手仕事が重視される古民家では、こうした専門業者に依頼することで、見た目と耐久性の両立が叶います。
注意点
- 一般業者より費用が高めになる場合あり
- 希少な自然塗料を使用するため、納期に時間がかかることも
とはいえ、「あと30年この家に住みたい」「親から受け継いだ家を守りたい」という方にとっては、十分に投資価値のある選択肢といえるでしょう。
3. 建築士が在籍する地元工務店
特徴
- 外装塗装に加えて、下地の腐食・構造のゆがみ・雨漏りなどにも対応可能
- 地元密着の工務店であれば、気候・風土に適した塗料や工法を熟知
- 建築士や大工と連携し、必要に応じて改修工事や構造補強も可能
メリット
- 「塗って終わり」ではなく、建物全体の寿命を延ばすための提案が受けられる
- 補助金や空き家再生事業に詳しい業者も多く、手続き面も安心
- 将来的な間取り変更やリノベーションにもつながる関係性が築ける
注意点
- 「外装塗装の仕上がり」に関しては、塗装専門業者に劣る場合もある
- 職人のスケジュールが埋まりやすく、時期によっては着工まで時間がかかることも
古民家塗装の費用相場と内訳

| 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 外壁塗装(漆喰・土壁) | 100〜150万円程度 |
| 木部塗装(柱・梁など) | 30〜80万円程度 |
| 屋根塗装(トタン・板金) | 50〜100万円程度 |
| 自然塗料の施工 | 通常よりも1.2〜1.5倍の費用 |
| 付帯部の補修や足場設置費 | 別途必要 |
※劣化状況・施工面積・塗料の種類によって大きく変動します。現地調査と見積もりが必須です。
古民家塗装業者選びで失敗しないチェックポイント

古民家塗装は、新築住宅の外壁塗装とはまったく別物です。築年数が長く、木材や漆喰など天然素材が多く使われている古民家では、素材ごとに適した塗料や施工方法の選定が不可欠。そのため、塗装業者の選び方を誤ると、美観や耐久性を損ねるだけでなく、建物の劣化を早めてしまうこともあります。
ここでは、古民家塗装で失敗しないために押さえておくべき業者選びのチェックポイントを詳しく解説します。
1. 古民家塗装の実績があるか?
まず最も重要なのが、古民家塗装の経験や施工実績があるかどうかです。
一見すると「外壁塗装のプロなら誰でもできるのでは?」と思われるかもしれませんが、古民家は使用されている建材・構造が特殊なため、通常の住宅と同じように塗装してもうまくいかないケースが多くあります。
例えば、木材の含水率を見極めて塗装を行わないと、塗膜の膨れや剥がれの原因になるほか、漆喰に不適切な塗料を使うと、化学反応でひび割れや白化現象を引き起こすことも。
そのため、業者のホームページやパンフレットを確認し、実際に古民家の施工事例があるかどうかを確認しましょう。「どのような素材に、どんな塗料を使い、どのような仕上がりになったか」まで具体的に記載されていると安心です。
2. 塗料の種類と特徴を丁寧に説明してくれるか?
古民家に使用される塗料にはさまざまな種類があり、それぞれに長所・短所・適材適所があります。
たとえば、
- 自然塗料(亜麻仁油、柿渋など):通気性が高く、木の呼吸を妨げない。環境にも優しいが耐久性にやや劣る。
- 造膜型塗料(ウレタン、シリコンなど):撥水性が高く高耐久。ただし木の呼吸を妨げる可能性があるため、選定には注意。
- 漆喰専用塗料(石灰ベースなど):吸湿性・調湿性を活かした塗料で、古民家の漆喰壁との相性がよい。
これらを正しく説明し、「どの塗料をどの部位に使うか」について丁寧に説明してくれる業者は、施工経験が豊富で誠実な対応ができる可能性が高いです。逆に、「おまかせください」「この塗料が一番です」と一方的に決めつける業者には注意しましょう。
3. 「一式見積もり」ではなく、明細付きか?
古民家塗装は手間がかかるぶん費用も高くなりがちです。そのため、見積もりの内容が明確でないと、「思っていたより高かった」「追加費用が発生した」といったトラブルにつながります。
信頼できる業者であれば、以下のような明細をしっかり記載してくれます。
- 使用塗料の種類と缶数、単価
- 下地処理や洗浄などの工程ごとの施工費
- 足場代、養生費
- 雑費(残材処理、交通費など)
「外壁塗装一式:〇〇万円」としか書かれていない見積書は、後からのトラブルの元。項目ごとの費用が明示されているかを必ず確認しましょう。
4. 地域の風土や建物の状況に詳しいか?
古民家は全国各地に存在しますが、地域によって建物の構造や塗装の耐候性は大きく異なります。たとえば、雪の多い地域では融雪剤や凍結への配慮が必要ですし、海沿いの地域では塩害対策が欠かせません。
そのため、地域密着型の業者で、その土地ならではの気候・風土に応じた塗料選びや施工方法を熟知していることが重要です。
地元で長く営業しており、「この地域での古民家施工実績があります」と言える業者であれば、施工中やアフターケアもスムーズに対応してくれるはずです。
まとめ
古民家塗装は、素材や構造への深い理解が必要です。自然塗料・木部・漆喰などへの特殊な塗装技術も求められるため、一般的な塗装業者では対応しきれないことも少なくありません。そのため、この分野の専門知識を持った業者選びが非常に重要になります。確かに費用は一般住宅より高めになりがちですが、大切な古民家の耐久性を高め、美しい景観を守るための必要な投資と考えるとよいでしょう。施工事例をしっかり確認し、詳細な見積もりを出してもらい、対応の丁寧さを見極めることが、信頼できる業者選びの成功につながります。
古民家塗装は、その建物の歴史や構造を十分に理解したうえでの施工が求められます。
全国の優良業者が集まる「ペイントGO」では、古民家塗装の実績豊富な塗装業者を簡単に探すことができます。お住まいの地域別で検索できるほか、自然塗料・漆喰などの対応分野で絞り込むことも可能です。また、気になる業者には無料で見積もり依頼や直接相談もできますので安心です。