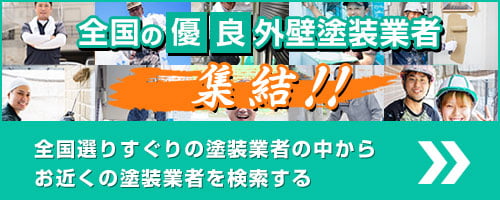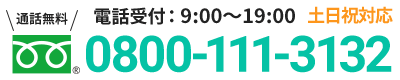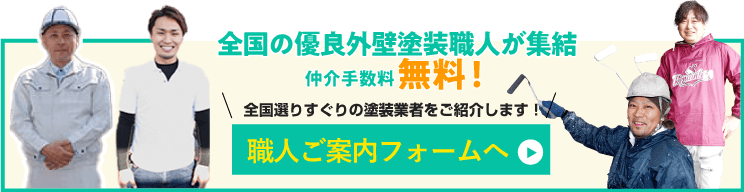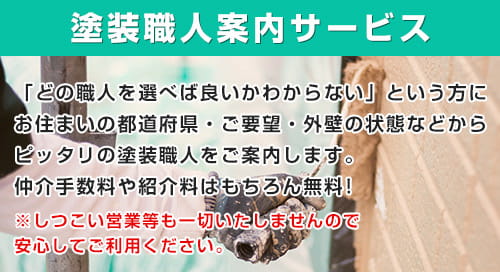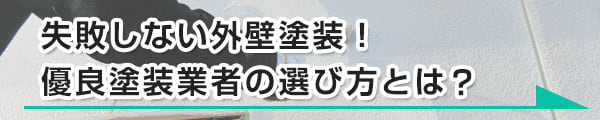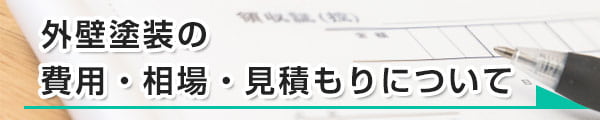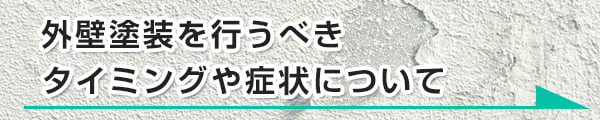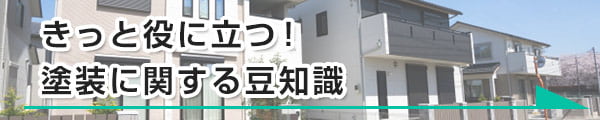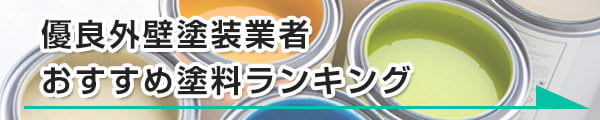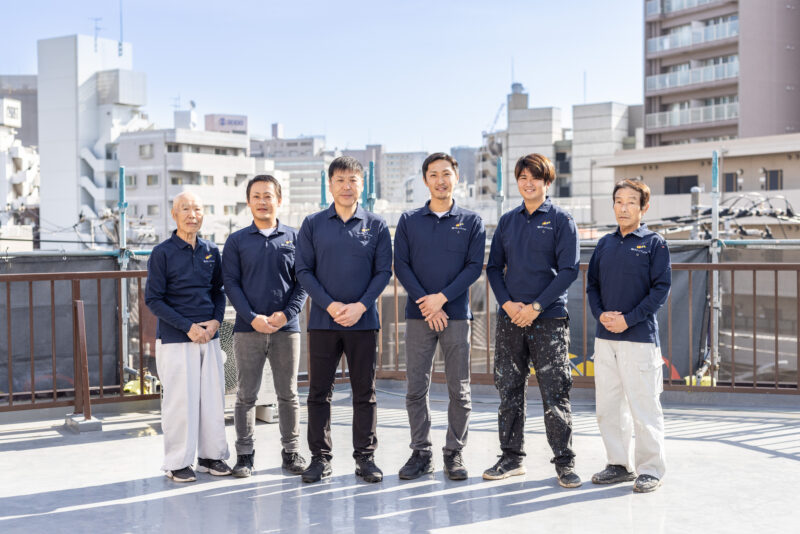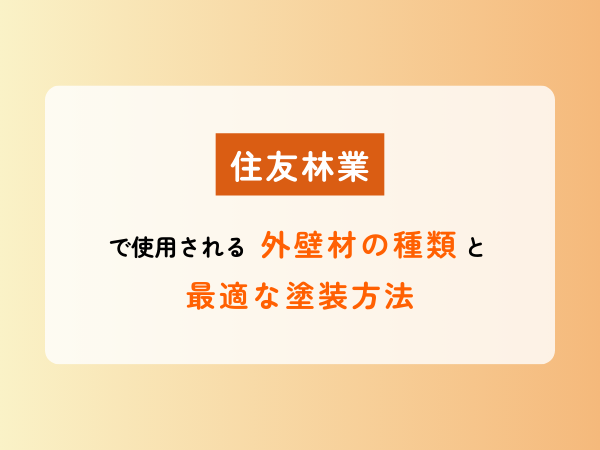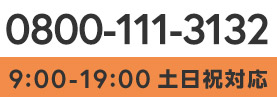使用する塗料の種類とグレード

塗料の違いで耐用年数も費用も大きく変わる
外壁塗装の見積もりを比較するうえで、最も注目すべき項目のひとつが「使用する塗料の種類とグレード」です。塗料は単に色をつけるだけでなく、建物を雨・風・紫外線から守る重要な役割を果たしています。そのため、どの塗料を使うかによって、耐用年数・メンテナンスサイクル・費用に大きな差が生まれます。
特に近年では、技術の進歩によりさまざまな機能性塗料が登場しており、各家庭のニーズや予算、立地条件によって最適な塗料選びが求められます。
以下に代表的な塗料の種類と特徴をまとめました。
主な塗料の種類と特徴
| 塗料の種類 | 耐用年数 | 特徴 | 適した用途 |
|---|---|---|---|
| アクリル系塗料 | 約3~5年 | もっとも価格が安価な塗料。現在では住宅用としてはあまり使われない。 | 仮住まいや短期的な利用を想定する建物向け |
| ウレタン系塗料 | 約6~8年 | アクリルより耐久性があり、価格も比較的安価。柔らかく密着性が高い。 | 細かい箇所や付帯部の塗装に適している |
| シリコン系塗料 | 約8~12年 | 耐久性・価格・仕上がりのバランスが非常に良い。現在の住宅塗装では最も使用されている。 | コスト重視と長寿命を両立させたい住宅 |
| ラジカル制御型塗料 | 約12~15年 | 紫外線による塗膜の劣化を抑える「ラジカル制御」機能が特徴。価格はシリコンよりやや高め。 | コストパフォーマンスの高い選択肢として注目 |
| フッ素系塗料 | 約15~20年 | 非常に耐久性が高く、公共施設やビルなどにも使われる高性能塗料。初期費用が高い。 | 塗り替え回数を減らしたい、長く住む予定のある住宅 |
| 無機塗料 | 20年以上 | 紫外線や熱、汚れに対する耐性が極めて高く、最長クラスの耐用年数。初期投資は高額。 | 一生に一度の塗り替えを目指す方に人気 |
塗料選びで注意すべきポイント
同じ「外壁塗装」という工事でも、使用する塗料のグレードによって最終的な費用に10万円〜50万円以上の差が生じることもあります。そのため、見積書には以下の点が明記されているかを必ずチェックしましょう。
塗料の正式名称とメーカー名
「シリコン塗料」とだけ書かれていても詳細が分かりません。たとえば、「日本ペイント/パーフェクトトップ」「関西ペイント/アレスダイナミックTOP」など、メーカーと商品名まで記載されていると安心です。
使用量や塗布面積
塗料の性能を発揮させるためには、規定の量を正しく塗布することが大前提。極端に少ない量で見積もられている場合は、手抜き施工の可能性もあります。
塗料の性能資料やカタログの提示
きちんとした業者であれば、どの塗料を使うかを説明する際にメーカーのカタログや比較表を使って丁寧に解説してくれるはずです。
塗装回数と工程の記載

「3回塗り」が基本。工程数に注意!
外壁塗装の仕上がりと耐久性に大きな影響を与えるのが、「塗装回数」と「工程の正確さ」です。一般的な塗装工事では、
- 下塗り(プライマーやシーラーなど)
- 中塗り(塗膜の厚みと色ムラ補正)
- 上塗り(最終仕上げ・美観・耐久性)
の3回塗りが基本の工程とされています。この3工程を丁寧に行うことで、塗料本来の性能が発揮され、長持ちする外壁に仕上がります。
しかし、見積書の中には「2回塗り」と書かれているものもあるため注意が必要です。たとえば、
- 下塗り+上塗りのみ
- 中塗りと上塗りを兼ねる2回塗り(工程短縮)
といったケースがあり、こうした施工では塗膜の厚みが不足し、数年で剥がれや色あせが起きるリスクが高まります。短期的にはコストが抑えられるように見えても、結果として再塗装のサイクルが早まり、トータルコストが上がることにつながります。
また、見積書に「3回塗り」と書かれていても、実際の工程や使用塗料が曖昧に書かれている場合は要注意。特に以下のような表記には気をつけましょう。
- 「塗装一式」などの簡易表記
- 中塗りと上塗りの塗料が同じか不明
- 工程ごとの塗布量や乾燥時間の記載がない
こうした不明瞭な内容の見積もりでは、手抜き工事や塗料の節約が行われるリスクがあるため、必ず以下のような項目が明記されているかを確認しましょう。
- 工程ごとの回数(例:下塗り1回、中塗り1回、上塗り1回)
- 各工程で使用する塗料の名称とメーカー
- 乾燥時間や重ね塗りの間隔に関する記述
信頼できる業者であれば、こうした工程を事前に説明し、必要に応じて工程表や仕様書を提示してくれます。価格だけで判断せず、工程の透明性と説明の丁寧さも、業者選びの大切な指標です。
▼見積書の項目参考例

足場代・養生費の有無と金額
工事全体の約15〜20%を占める足場費用

外壁塗装の見積もりで「塗装費用」ばかりに注目しがちですが、実は足場代や養生費が大きな割合を占めていることをご存知でしょうか。
特に足場代は、2階建ての一般的な住宅で15万〜25万円程度が相場です。塗装工事では高所での作業が多いため、安全確保と作業効率を高めるために足場の設置は欠かせません。
ただし、見積書の中には以下のような表記をしてくる業者もあります。
- 「足場代無料」
- 「サービス」
- 「キャンペーンで値引き中」
こうした場合、注意が必要です。実際には別の項目に上乗せされていたり、塗装単価が割高になっていたりするケースがあるため、「無料だからお得」とは限りません。見積もりを比較する際は、全体金額の内訳をしっかりチェックし、総合的に妥当かどうかを判断することが重要です。
養生費の確認も忘れずに
.jpeg)
もう一つの見落としがちな費用が「養生費」です。養生とは、塗装しない箇所(窓・ドア・植栽など)をビニールや養生テープなどで保護する作業で、外壁塗装においては非常に重要な工程です。
この養生作業が丁寧に行われていないと、
- 塗料の飛散による汚れ
- 作業ミスによる部材の劣化
- 美観の損失
などのトラブルにつながります。
養生費についても、見積もりに「一式」とまとめて記載されている場合は注意が必要です。信頼できる業者であれば、
- 養生面積(㎡)×単価(円)
- 養生内容(ビニール・マスカー・布テープなど)
- 作業範囲(窓・玄関・植木など)
といった具体的な内訳が示されています。
下地補修・高圧洗浄の範囲
.jpeg)
劣化の状態によって補修内容が大きく異なる
外壁塗装は単に色を塗る作業ではありません。塗料をしっかり密着させて長持ちさせるためには、「下地の処理」が何よりも重要です。その中でも代表的なのが「下地補修」と「高圧洗浄」です。
まず、下地補修では、外壁に見られる劣化の種類や程度によって、適切な処置方法が求められます。主な補修内容には以下のようなものがあります。
クラック(ひび割れ)補修
幅0.3mm以下のヘアークラックなら、シーリング材の充填で済むこともありますが、0.3mm以上の構造クラックの場合は「Vカット工法」などのしっかりとした補修が必要です。これを怠ると、内部に雨水が侵入して塗膜の剥がれや建物内部の腐食につながります。
サイディングの浮きや反りの補正
張り直しやビス止めによって補正が可能です。表面の塗装だけではごまかせないため、見積もりに「浮き補修」や「部分張り替え」の記載があるか確認しましょう。
シーリングの打ち替え
サイディングボードの継ぎ目に使われるシーリング(コーキング)は経年で硬化・ひび割れが起こります。これを放置したまま塗装しても、防水性が確保されないため、雨漏りの原因になります。見積書には「打ち増し」か「打ち替え」か明記されているかをチェックしてください。
次に高圧洗浄についても、見積書で明確に記載されているかが重要です。高圧洗浄は、チョーキング(白い粉)やカビ・藻・ホコリをしっかり落とす作業で、これを怠ると塗料が密着せず早期剥がれの原因になります。
見積もりを比較する際には、
- 洗浄対象は外壁のみか、屋根・雨樋・塀・付帯部まで含むのか
- 「㎡単価」か「一式」か
- 苔や藻の除去に薬品処理が含まれているか(バイオ洗浄など)
といった細かな違いに注目しましょう。
下地補修と高圧洗浄は、「塗装の品質を左右する土台づくり」です。価格だけでなく、どこまで丁寧に下準備されているかを見極めることが、長持ちする外壁塗装への第一歩です。
保証内容とアフターサポート

工事後も安心できる業者かどうかを見極める
外壁塗装は決して安い買い物ではありません。だからこそ、「塗ったら終わり」ではなく、「その後も安心して暮らせるかどうか」が非常に重要です。
見積もり段階で必ず確認すべきなのが、保証内容の有無とその内容です。外壁塗装には大きく分けて2種類の保証があります。
施工保証(工事保証)
これは塗装工事の施工ミスや不具合が原因で、塗膜に不具合が生じた場合に適用される保証です。たとえば、以下のような事象が対象になります。
- 塗料が短期間で剥がれた
- 塗りムラ・塗り残しがあった
- ひび割れが再発した
施工保証の期間は業者によって異なりますが、5〜10年が一般的な目安です。短すぎる保証しか付かない場合は、施工に自信がない表れかもしれません。
塗料保証(メーカー保証)
こちらは、塗料自体に問題があった場合に、メーカーが保証する制度です。性能に対して問題があった場合、再塗装や補修費用が補償されることがあります。ただし、すべての塗料に保証が付いているわけではなく、一定の条件(指定業者による施工など)を満たす必要があります。
- ラジカル塗料:10〜12年保証が多い
- フッ素系・無機塗料:15年保証がつくことも
- アクリル系:基本的に保証なし
見積もりの中に、「塗料保証の有無」と「保証期間」が明記されているかを確認しましょう。
アフターサービス・定期点検
保証と合わせて重要なのが、工事後のフォロー体制です。優良業者であれば、工事完了後に定期点検(1年・3年・5年など)を行って、塗装の状態をチェックしてくれます。
さらに、万が一不具合が見つかった場合に迅速に対応してくれるかどうかも確認ポイントです。トラブルが起きた際に電話がつながらない・対応が遅いなどでは、せっかくの保証も無意味になってしまいます。
保証書の発行があるか
見積もり時点で「保証書を発行します」と説明されるかどうかも、業者の誠実さを測るバロメーターです。保証書には、
- 保証対象と保証範囲
- 保証期間
- 保証の条件(例:故意の破損は除く等)
などが明記されている必要があります。
総額だけでなく「内訳の明細」も確認
安い見積もりに潜む「一式」「〇〇含む」のワナ
外壁塗装の見積もりを受け取ったとき、つい目が行きがちなのが「総額」です。しかし、総額だけを見て契約を決めるのは非常に危険です。見積書の内訳を細かく確認しなければ、後々になって「そんな工事は含まれていない」「これは別途費用がかかります」といった追加請求のトラブルに発展する恐れがあります。
特に注意したいのが、「一式」や「○○含む」といった曖昧な表現が多用されている見積書です。
「一式」表記の多用は要注意
たとえば、「足場設置:一式」「下地処理:一式」「付帯部塗装:一式」といった表現だけの見積書では、具体的にどの作業が含まれているのか分かりません。仮に工事中に「この作業は含まれていないので追加費用になります」と言われても、施主側としては反論しにくくなります。
信頼できる業者であれば、以下のように数量 × 単価で具体的に記載されています。
- 足場設置:200㎡ × 800円 = 160,000円
- 軒天塗装:30m × 500円 = 15,000円
- 雨樋塗装:40m × 600円 = 24,000円
このように明確に書かれているほど、誠実で透明性の高い見積もりであると判断できます。
実測値に基づいているか?
見積書に記載されている塗装面積が実際の建物サイズに基づいているかも非常に重要です。業者によっては、簡易的な図面や目視だけで面積を概算し、その数値で見積もりを出している場合もあります。
本来は、「現地調査」をしっかり行い、レーザー測定や実測による正確な面積算出が望まれます。見積書に「実測による面積」や「現場調査の結果に基づく」といった記載があると信頼性が高まります。
付帯部の塗装が含まれているか?
外壁塗装といっても、実際の工事範囲は外壁だけではありません。雨樋(あまどい)・破風(はふ)・軒天(のきてん)・鼻隠し・雨戸・戸袋・ベランダの手すりなど、いわゆる「付帯部」も劣化するため、本来はあわせて塗装するべきです。
ところが、付帯部の塗装が見積もりに含まれていないケースも多々あります。その場合、契約後に「追加で〇万円かかります」と言われることもあるため要注意です。
以下のような記載があるかを確認しましょう。
- 雨樋塗装:〇m × 単価
- 軒天塗装:〇m² × 単価
- 破風板塗装:〇m × 単価
「外壁以外のどこまで塗装してもらえるのか」を、明細の内訳でしっかりチェックすることが、後悔しない見積もり選びの第一歩です。
曖昧な表現がある場合は必ず質問を
「この『一式』には何が含まれますか?」
「追加費用が発生するケースはありますか?」
「この塗装面積はどうやって算出しましたか?」
このような質問を投げかけたときに、丁寧に答えてくれるかどうかも、業者選びの大切な判断材料です。
まとめ
外壁塗装は、決して安い買い物ではありません。「価格が安いから」と安易に決めてしまうと、後から追加費用が発生したり、工事の品質に不満が残ることもあります。
失敗しないためには、見積もりの中身をしっかり比較することが大切です。以下の6つのポイントは必ずチェックしましょう。
- 使用する塗料の種類とグレード
- 塗装回数と工程の記載
- 足場代・養生費の明細
- 下地補修・高圧洗浄の内容
- 保証内容とアフターサポート
- 内訳の明細が明確か
「どの見積もりを信じていいのかわからない…」「業者選びに不安がある…」という方は、外壁塗装の専門ポータル【ペイントGO】をぜひご活用ください。
- 専門スタッフが選定した優良業者のみを紹介
- 見積もり比較や塗料の相談もサポート
- 全国対応・地元密着業者が多数登録
納得できる外壁塗装を実現するために、まずはペイントGOでの情報収集から始めてみましょう。失敗しない工事の第一歩は、正しい業者選びからです。